治療から予防へ 歯科医院経営の転換戦略
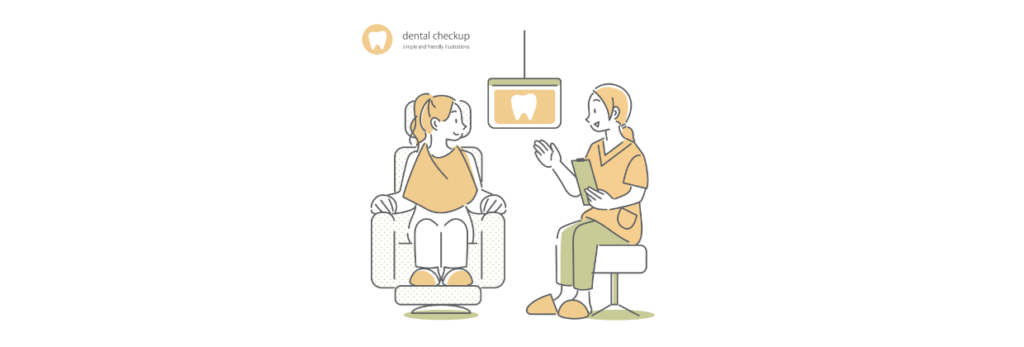
近年、歯科医院を取り巻く経営環境は大きく変化しています。
その主な要因として、患者さんの意識や行動の変化が挙げられます。特に社会全体のデジタル化の進展に伴い、歯科医院の運営や患者さんとの関わり方にも新たなアプローチが求められるようになりました。さらに、国の予防歯科推進政策も相まって、従来の治療中心から予防中心への経営転換が注目されています。
本記事では、予防歯科経営が歯科医院にもたらす具体的なメリットや実践方法、転換時の注意点について詳しく解説します。
予防歯科経営が必要な理由
まずは予防歯科経営への転換が求められる背景について解説します。
歯科医院を取り巻く環境の変化
インターネット環境の普及により、患者さんの行動パターンが大きく変わりました。患者さんが容易に情報を入手できるようになった結果、歯科医院選びの判断基準も多様化し、口コミや評判、医院のサービス内容などを事前に調べてから来院することが増えました。この変化により、歯科医院はより積極的に選ばれる努力が必要になっています。
このような患者さんの変化に対応するには、デジタル化への取り組みが重要です。自医院のWebサイトでの分かりやすい情報発信、オンライン予約システムの導入、SNSを使った日常的な情報提供など、デジタルを活用したコミュニケーションが患者との関係を築くうえで欠かせません。
また、厚生労働省による予防歯科の推進や医療DXの取り組みが本格化しており、歯科医院も国の政策方針に沿った対応が求められています。こうした時代の流れに対応していくことが、患者さんから選ばれ続ける医院になるために必要な要素となっています。
●あわせて読みたいお役立ち資料:「歯科医院のホームページ開設入門ガイド」はこちら
患者さんの意識変化と予防ニーズの高まり
このような環境変化に加えて、患者さん側の意識にも変化が見られます。『痛くなったら治療する』から、『病気になる前に予防する』へと意識が変わりつつあり、特に中高年層では、将来の医療費負担を抑制したいというニーズから、予防的な取り組みへの関心が高まっています。
この予防志向の高まりは、患者さんのニーズの多様化にもつながっています。単純な治療だけでなく、口腔全体の健康維持や美容面でのケアを希望する声が増えており、歯科医院にはより幅広いサービスの提供が求められるようになっています。
日本歯科医師会による予防歯科推進の動き
こうした患者さんの意識変化を背景に、業界全体でも予防歯科への取り組みが本格化しています。特に、厚生労働省の予防歯科推進を受けて、日本歯科医師会でも予防歯科を重視する取り組みが進められています。同会が発表した「2040年を見据えた歯科ビジョン」では、従来の治療中心から、予防・管理中心への転換を打ち出しており、国の政策方針と歩調を合わせた動きとなっています。
このビジョンでは、患者さんが生涯を通じて口腔の健康を維持できることを目指し、「かかりつけ歯科医」としての役割強化や地域包括ケアへの積極的な関わりを重要な方針としています。
参考:2040年を見据えた歯科ビジョン|日本歯科医師会
予防歯科経営のメリット
予防歯科経営が歯科医院にもたらすメリットを、収益面や患者関係、スタッフ面から紹介します。
安定した収益の確保
予防歯科経営では、従来の治療中心の経営に比べ、収益の変動を抑えやすくなります。治療は患者さんの症状や必要性によって収益が大きく左右されますが、予防歯科では定期的なメンテナンスを通じて安定的な収益を見込めます。
特に、歯科衛生士による継続的なメンテナンスにより、定期患者数に応じた収益基盤を築ける点は大きなメリットです。さらに、予防処置は技工料や材料費が少なく、利益率が高いという特徴もあります。
患者さんとの長期的な関係構築
予防歯科では、患者さんと長期的な関係を築きやすくなります。定期的なメンテナンスを通じて口腔内の変化を継続的に把握し、一人ひとりに合わせたケアを行うことが可能です。このような継続的な関わりを通じて、信頼関係を築くことができます。
こうした信頼関係は患者満足度の向上にもつながります。痛みが出てから慌てて治療するのではなく、健康な状態を保てることで、患者さんは「この医院に通っていてよかった」という安心感を持つことができます。
その結果、満足した患者さんからの紹介も自然と増えてきます。口コミで新しい患者さんを獲得できれば、広告費をかけずに医院の成長につなげることができます。
スタッフのやりがい向上
予防歯科に取り組むことで、歯科衛生士が自分の専門性を発揮しやすい環境が整います。治療の補助だけでなく、予防の専門家として患者さんと向き合える機会が増えるため、やりがいも高まります。
さらに、長く患者さんの健康を支えることで、医療従事者としての充実感に加え、コミュニケーション能力や知識の幅も自然と広がります。こうした働きがいのある環境は、スタッフの定着率向上にも効果的です。歯科衛生士不足が続く今、優秀な人材を定着させるうえでも、予防歯科に取り組むことは大きな意味があります。
地域での信頼関係構築と認知度向上
予防歯科に取り組むことで、歯科医院は「痛くなったら行く場所」から「健康を守るパートナー」として認識されるようになります。その結果、地域の人々からの信頼も自然と高まります。
また、予防を重視している医院は、地域での認知度向上につながります。「治療だけでなく予防にも力を入れている」という印象は、患者さんが医院を選ぶ理由のひとつです。
さらに、地域の健康づくりに積極的に関わることで、自治体や地域団体との連携の機会も増えていきます。健康講座や学校歯科健診などを通じて地域と関係を築くことで、長期的な信頼関係の構築につながります。
予防歯科経営の取り組み方
予防歯科経営を効果的に実践するための方法や体制づくりのポイントを解説します。
患者さんへの予防意識の啓発
予防歯科経営を効果的に進めるには、患者さんに予防の重要性を理解していただくことが大切です。
しかし、多くの患者さんは予防が大事だと分かっていても、具体的にどうすればよいのか、なぜ継続が必要なのかといった点まで詳しく理解できているとは限りません。
効果的な情報共有には、視覚的な資料の活用がおすすめです。口腔内写真や模型を使用して、現在の状態を分かりやすく説明し、将来のリスクを具体的に示すことで、患者さんの予防意識を高められます。
また、自医院のWebサイトでの情報提供やブログ・動画の配信、SNSアカウントを使った日常的な予防情報の発信など、デジタルツールを活用することで、来院時以外でも継続的に予防の大切さを伝えやすくなります。
さらに、患者さん一人ひとりの生活習慣や口腔内の状態に応じて、個別の予防プログラムを提案することも大切です。画一的な説明ではなく、患者さんに合わせた取り組みにより、継続率の向上が期待できます。
お問い合わせが多い関連サービス
歯科衛生士中心の予防体制
予防歯科を効果的に進めるには、歯科衛生士を中心とした体制づくりが大切です。特に担当制を導入すると、同じ衛生士が継続して患者さんを見ていけます。そのため小さな変化にも気づきやすく、一人ひとりに合ったケアにつなげることができます。
また、歯科衛生士のスキルアップも欠かせません。最新の予防技術や機器の活用法、患者さんとのコミュニケーション技術などを学べる機会を提供することで、予防処置の質向上につながります。
予防処置プログラムの充実
定期的なクリーニング、歯石除去、フッ素塗布、歯科衛生士によるブラッシング指導などを組み合わせたメンテナンスプログラムから、SRPやPMTCのプログラムを導入することも効果的です。インプラント治療を受けた患者さんには、専用のメンテナンスプログラムを自費診療として整備することも重要です。
また、継続的な予防効果を得るためには、リコール体制の構築と運用が欠かせません。患者さんの口腔状態に応じてメンテナンス間隔を適切に設定し、定期的な来院を促すシステムを整備することで、継続的なケアが可能になります。デジタルツールを活用した自動リマインド機能や、患者さんが予約を取りやすいオンライン予約システムの導入により、継続率の向上を図ることができます。
お問い合わせが多い関連サービス
予防歯科経営への転換で注意すべきこと
治療中心から予防中心への経営転換を進める際に押さえておくべきポイントを紹介します。
段階的な移行計画
治療中心から予防中心への移行は、段階を踏んで進めることで無理なく実現できます。まずは、現在通院している患者さんのうち治療が終わった方に定期メンテナンスを勧めるところから始めると移行しやすくなります。既に信頼関係がある患者さんであれば、予防の必要性も理解してもらいやすく、移行もスムーズに進みます。
新しく来院した患者さんには、初診時から予防の大切さを伝え、治療が終わった時点で定期メンテナンスの合意を早めに得ることがポイントです。治療と予防をセットで考える意識を医院全体に根づかせることで、予防歯科経営の基盤づくりにつながります。
スタッフの意識改革
こうした経営モデルの転換には、スタッフの理解と協力が必要です。特に、治療補助が中心だったスタッフが予防の専門家として活動するには、意識面でのサポートが欠かせません。
そのために役立つのが定期的な院内研修です。予防歯科の意義や効果を学ぶだけでなく、実際の取り組み事例や患者さんからの感謝の声を共有することで、スタッフの理解やモチベーションの向上につながります。さらに、定期患者数の推移や収益への貢献度を数値として示すことで、取り組みの意義を実感できるようになります。
まとめ
予防歯科を中心とした経営は、歯科医院の持続的な成長を支える重要な戦略です。患者さんの健康を長期的に守りながら、医院としても安定した収益基盤を築き、スタッフにとってやりがいのある職場環境を整えることができます。
ただし、治療型から予防型への転換は容易ではありません。患者さんやスタッフに予防の意義を理解してもらいながら、時間をかけて少しずつ変化を浸透させていくことが欠かせません。
予防歯科経営は収益性の向上にとどまらず、患者さんの長期的な口腔健康を支えるうえでも価値のある取り組みです。このような視点で取り組むことで、医院の成長と患者さんの健康維持の両立を目指せます。
あわせてよく読まれるコラムはこちら
●関連コラム:「歯科医院の集患に効果的な対策のポイントとは?」はこちら
●関連コラム:「歯科衛生士はどうして定着しないのか?その理由と対策を考える」はこちら
●関連コラム:「歯科衛生士不足が続く歯科業界、定着率を上げるためのポイントとは」はこちら
│投稿者│株式会社ミック デジタルマーケティングチーム
株式会社ミックが運営する歯科医院さま向けのコラムです。
弊社デジタルマーケティングチームが歯科にまつわるトレンド情報を定期的に発信しています。